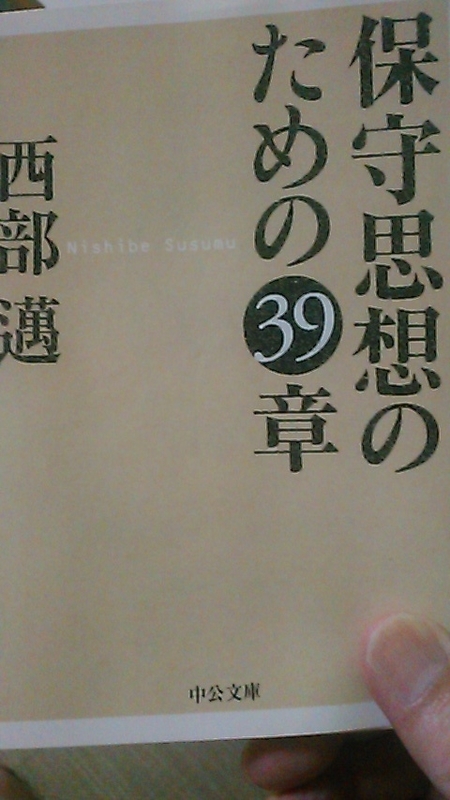
「「戦後」の完成-アプレゲールの末路 - 西部邁」中公文庫 保守思想のための39章 から
アメリカ帝国主義は、その純粋な観念型としては、実は日本において開示されている。それは、戦後日本の、いわゆる「敗戦のトラウマ(精神の癒えぬ外傷)」に発する、先勝国アメリカへの過剰適応の結果だといってよい。
心理学の用語にイントロジェクション(摂取)の自己防衛というのがあるが、戦後日本は「摂取」の心理的メカニズムにとらわれてきた。つまり日本のアプレゲール(大戦後派)は、少なくとも観念の領域では、「アメリカ的なるもの」の摂取をもって文明の「進歩」とみなしてきたのである。そして観念の領域を代弁するのが知識人なのであってみれば、そういう進歩主義者の群れの先頭にアプレゲールの知識人がいる。
そのことを端的に示すのがかつて小泉内閣が掲げた「聖域なき構造改革」である。その改革は、進むにつれて日本の現状をいっそう惨憺たるものにしたのは明らかである。それにもかかわらず、国民はいっとき、圧倒的な支持を与えた。その支持が本気のものかどうかについては諸説あるとはいえ、日本国民はそれを支持するというポーズを示したのは間違いない。そうなるのは、小泉改革が「アメリカ的なるもの」にしっかりと方向づけられていたからである。つまり、アメリカというより高次の聖域に近づくのに邪魔になる日本というより低次の聖域をすべて破壊する、それがこの改革の趣旨だったのだ。
その意味で、当時、小泉首相が自分のことを「根っからの親米派」とよんだのは正確な発言であった。事実後段で触れるように、この改革にあっては、経済における市場主義といい政治における世論主義といい、アメリカニズムを奉じるのを金科玉条としている。そうみなすのでなければ、アメリカにあってすら様々に失態をさらしているアメリカニズムに日本人の大半が寄り添っていくこの光景をうまくとらえることができない。それは丁度、植民地にあって本国の文明が、過剰に単純化され大量に花開く、という歴史上いくつもみられた事例を思い出させる。
明治維新から過ぐる敗戦に至るまでの七十七年間にも、欧米文化の摂取をただちに文明の進歩とみなす傾きはあった。しかしそれへの反動としての(高山樗牛[ちょぎゅう]たちがいったところの)「日本主義」もしばしば激甚に及んだ。それがついには大東亜戦争を惹起[じゃっき]させもした。大東亜戦争の敗戦後においては、そうした反動はあったとしてもごく微弱であった。一九八〇年代、日本の経済的成功を称えるべく「日本的経営」の礼賛が行われた。しかしそれとて、バブル経済が崩壊したあとでは、ほかならぬ日本的経営が企業の構造改革の桎梏[しっこく]なのだと指弾されている始末である。
今から五十七年の一九五六年、(経済的にみて)「もはや戦後ではない」といわれ、今から二十年前には(政治的にみて)「戦後の総決算」が必要だといわれた。しかし、七十年近い「戦後」の舵取りにとって方向指示を与えてきたのは「アメリカ的なるもの」であった。アメリカが文明のクライテリオン(規準)を与えるという思想は強化されるばかりであった。つまり進歩と退歩とを分かつ臨界的な規準はアメリカからやってくるという考え方が次第に強くなってきたのである。そうした(観念における)アメリカ帝国主義への屈従の姿勢こそが「戦後」的精神の真相なのであった。その意味では、「聖域なき」という改革の形容は「日本なき」と同義なのである。したがって今の日本は「戦後の完成」を目の当たりにしているということになる。
アメリカ帝国主義は、その純粋な観念型としては、実は日本において開示されている。それは、戦後日本の、いわゆる「敗戦のトラウマ(精神の癒えぬ外傷)」に発する、先勝国アメリカへの過剰適応の結果だといってよい。
心理学の用語にイントロジェクション(摂取)の自己防衛というのがあるが、戦後日本は「摂取」の心理的メカニズムにとらわれてきた。つまり日本のアプレゲール(大戦後派)は、少なくとも観念の領域では、「アメリカ的なるもの」の摂取をもって文明の「進歩」とみなしてきたのである。そして観念の領域を代弁するのが知識人なのであってみれば、そういう進歩主義者の群れの先頭にアプレゲールの知識人がいる。
そのことを端的に示すのがかつて小泉内閣が掲げた「聖域なき構造改革」である。その改革は、進むにつれて日本の現状をいっそう惨憺たるものにしたのは明らかである。それにもかかわらず、国民はいっとき、圧倒的な支持を与えた。その支持が本気のものかどうかについては諸説あるとはいえ、日本国民はそれを支持するというポーズを示したのは間違いない。そうなるのは、小泉改革が「アメリカ的なるもの」にしっかりと方向づけられていたからである。つまり、アメリカというより高次の聖域に近づくのに邪魔になる日本というより低次の聖域をすべて破壊する、それがこの改革の趣旨だったのだ。
その意味で、当時、小泉首相が自分のことを「根っからの親米派」とよんだのは正確な発言であった。事実後段で触れるように、この改革にあっては、経済における市場主義といい政治における世論主義といい、アメリカニズムを奉じるのを金科玉条としている。そうみなすのでなければ、アメリカにあってすら様々に失態をさらしているアメリカニズムに日本人の大半が寄り添っていくこの光景をうまくとらえることができない。それは丁度、植民地にあって本国の文明が、過剰に単純化され大量に花開く、という歴史上いくつもみられた事例を思い出させる。
明治維新から過ぐる敗戦に至るまでの七十七年間にも、欧米文化の摂取をただちに文明の進歩とみなす傾きはあった。しかしそれへの反動としての(高山樗牛[ちょぎゅう]たちがいったところの)「日本主義」もしばしば激甚に及んだ。それがついには大東亜戦争を惹起[じゃっき]させもした。大東亜戦争の敗戦後においては、そうした反動はあったとしてもごく微弱であった。一九八〇年代、日本の経済的成功を称えるべく「日本的経営」の礼賛が行われた。しかしそれとて、バブル経済が崩壊したあとでは、ほかならぬ日本的経営が企業の構造改革の桎梏[しっこく]なのだと指弾されている始末である。
今から五十七年の一九五六年、(経済的にみて)「もはや戦後ではない」といわれ、今から二十年前には(政治的にみて)「戦後の総決算」が必要だといわれた。しかし、七十年近い「戦後」の舵取りにとって方向指示を与えてきたのは「アメリカ的なるもの」であった。アメリカが文明のクライテリオン(規準)を与えるという思想は強化されるばかりであった。つまり進歩と退歩とを分かつ臨界的な規準はアメリカからやってくるという考え方が次第に強くなってきたのである。そうした(観念における)アメリカ帝国主義への屈従の姿勢こそが「戦後」的精神の真相なのであった。その意味では、「聖域なき」という改革の形容は「日本なき」と同義なのである。したがって今の日本は「戦後の完成」を目の当たりにしているということになる。
それは、「日本的なるもの」のがわからいえば、自殺せんがために崖っ淵に立っていることを意味する。日本的なるものが消失することそれ自体に異を唱えても始まらないが、日本的なるものに支えられずに日本人ははたして活力を持って生きることができるのか、という重大な問いが残る。今、民間活力だの市場活力だのを囃す声はかまびすしい。しかし、「改革」とともに進んでいるのは日本人の活力のおびただしい衰弱ということでしかない。それが、日本の喪失の一つの帰結であることはどうやら疑うべくもないようである。
ここで「外から受け入れたあらゆる文明は、それを受けとる者にとっては容易に命取りとなる。なぜなら文明は文化と違って......国民生活のなかの浮わついた気分によって作られていく“奢侈”の総体だからである」(ホセ・オルテガ)という診断のことが思い起こされる。あるいは(夏目漱石の予言した)明治日本における「外発的文明の危機」のことを思い起こすべきかもしれない。
いずれにせよ、人間は理想を追う動物だとはいうものの、その理想形成の土台となる価値感覚や規範意識は、習俗の制度および慣習の仕組として、人間の実際知の現実に内在しているのでなければならない。そうでなければ理想追求はたちどころに腰砕けになる。アメリカニズムの理想は、それをひとまず是認したとしても、日本人の現実とは呼応していないのである。
いや、戦後日本の現実は、日本人の度外れの勤勉(もしくは屈従)のせいか、一時の中断もなくアメリカナイズされてきた。だが、その日本のアメリカ化それ自身が過剰に定型化されたものだったのである。たとえばフリーダムとデモクラシーについていえば、我が国には固有の形態での自由・民主が(どちらかといえば存分に)あった。あっさりいうと、日本には厳格な規制体系も強烈な権威体制もなかったために、自由・民主が成長しえたということである。
それは、もちろん日本的な自由・民主であった。なぜなら、日本的に曖昧な規制と日本的に隠微な専制がその自由と民主を裏打ちしていたからである。敗戦のあと、その自由・民主にイデオロギー的な粉飾がほどこされた。つまり規制と権威をさらに弱めること、それがアメリカン・フリーダムでありアメリカン・デモクラシーであるとみなされた。つまるところ、自由と民主を過剰に追求するのが理想とされたのである。
アメリカの場合、人種的にも宗教的にも、政治的にも法律的にも、かなりに厳しく規制の網目が張りめぐらされてきた。したがって自由の要求にも切迫味がこもっている。民主の要求についても然りであって、地位においても資産においても日本のとは比較にならないほどの大きな格差が存在しているアメリカ社会では、平等の要求とそれにもとづく民主の要求に衝迫味が宿るのである。
日本の場合といえば、アメリカの理想が宗教の如きものとして輸入されるや、それは日本の現実を破壊する凶器となった。その結果、無制約の自由・民主が戦後日本を彩ることとなった。理想と現実のあいだの緊張感が失われれば、理想はイデオロギーとして定型化され、ついには、そのイデオロギーに殉じた振りをしつづけるという空虚な現実が広がる。
保守思想の妙味はまさに現実と理想のあいだの対応を探るところにある。保守思想が「保守」するのは、現実がいかに理想によって率いられているか、そして理想がいかに現実にもとづいて構成されているか、という理想と現実の対応にかんする関心である。
この意味での保守的観点を戦後日本ほどあっさりと放棄した国はない。というより、理想と現実のあいだの対応関係は国ごとに異なることに着目すれば、戦後日本が保守しようとしなかったのは「国」の観念そのものだというべきかもしれない。そして、国の観念を放擲[ほうてき]した国の哀れな末路が我々の眼前にさらされている。保守思想への関心が喚起されなければならないのはここにおいてである。
ここで「外から受け入れたあらゆる文明は、それを受けとる者にとっては容易に命取りとなる。なぜなら文明は文化と違って......国民生活のなかの浮わついた気分によって作られていく“奢侈”の総体だからである」(ホセ・オルテガ)という診断のことが思い起こされる。あるいは(夏目漱石の予言した)明治日本における「外発的文明の危機」のことを思い起こすべきかもしれない。
いずれにせよ、人間は理想を追う動物だとはいうものの、その理想形成の土台となる価値感覚や規範意識は、習俗の制度および慣習の仕組として、人間の実際知の現実に内在しているのでなければならない。そうでなければ理想追求はたちどころに腰砕けになる。アメリカニズムの理想は、それをひとまず是認したとしても、日本人の現実とは呼応していないのである。
いや、戦後日本の現実は、日本人の度外れの勤勉(もしくは屈従)のせいか、一時の中断もなくアメリカナイズされてきた。だが、その日本のアメリカ化それ自身が過剰に定型化されたものだったのである。たとえばフリーダムとデモクラシーについていえば、我が国には固有の形態での自由・民主が(どちらかといえば存分に)あった。あっさりいうと、日本には厳格な規制体系も強烈な権威体制もなかったために、自由・民主が成長しえたということである。
それは、もちろん日本的な自由・民主であった。なぜなら、日本的に曖昧な規制と日本的に隠微な専制がその自由と民主を裏打ちしていたからである。敗戦のあと、その自由・民主にイデオロギー的な粉飾がほどこされた。つまり規制と権威をさらに弱めること、それがアメリカン・フリーダムでありアメリカン・デモクラシーであるとみなされた。つまるところ、自由と民主を過剰に追求するのが理想とされたのである。
アメリカの場合、人種的にも宗教的にも、政治的にも法律的にも、かなりに厳しく規制の網目が張りめぐらされてきた。したがって自由の要求にも切迫味がこもっている。民主の要求についても然りであって、地位においても資産においても日本のとは比較にならないほどの大きな格差が存在しているアメリカ社会では、平等の要求とそれにもとづく民主の要求に衝迫味が宿るのである。
日本の場合といえば、アメリカの理想が宗教の如きものとして輸入されるや、それは日本の現実を破壊する凶器となった。その結果、無制約の自由・民主が戦後日本を彩ることとなった。理想と現実のあいだの緊張感が失われれば、理想はイデオロギーとして定型化され、ついには、そのイデオロギーに殉じた振りをしつづけるという空虚な現実が広がる。
保守思想の妙味はまさに現実と理想のあいだの対応を探るところにある。保守思想が「保守」するのは、現実がいかに理想によって率いられているか、そして理想がいかに現実にもとづいて構成されているか、という理想と現実の対応にかんする関心である。
この意味での保守的観点を戦後日本ほどあっさりと放棄した国はない。というより、理想と現実のあいだの対応関係は国ごとに異なることに着目すれば、戦後日本が保守しようとしなかったのは「国」の観念そのものだというべきかもしれない。そして、国の観念を放擲[ほうてき]した国の哀れな末路が我々の眼前にさらされている。保守思想への関心が喚起されなければならないのはここにおいてである。