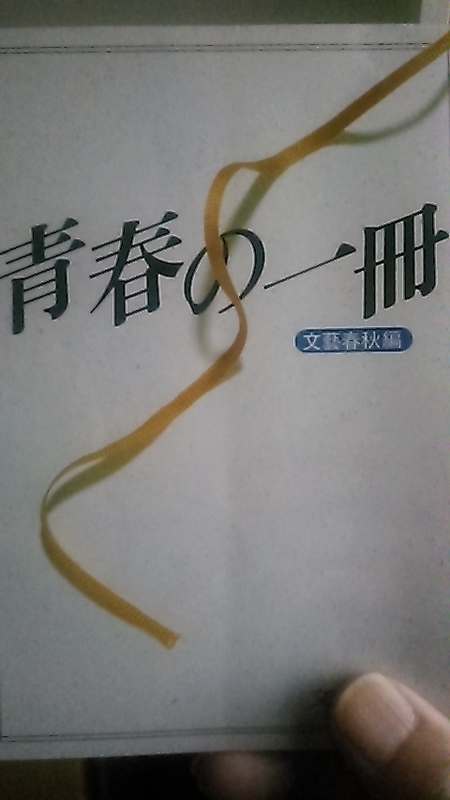
「柏原兵三『徳山道助の帰郷』 - 南木佳士」文春文庫 青春の一冊 から
本棚の文庫本の群れの中には、すでに紙が茶色く変色してしまっているものが数多くあるが、この本ほど何度も読み返してみたものはない。それなのに、いつから本棚に存在しているのか、これほど分からない本もない。
柏原兵三氏が『徳山道助の帰郷』で芥川賞を受賞した昭和四十三年、私は高校一年生であった。当時は芥川賞の名だけは知っていたが、まだ作品を読んだことはなかった。高校三年の夏休みが終わり、教室で再開した級友たちと、その年の上半期の芥川賞に決まった庄司薫氏の『赤頭巾ちゃん気をつけて』について話した記憶がある。東京の進学校と言われる高校にいたので、似た環境の高校生の心理を現代風なタッチで描いたこの作品は、級友たちに圧倒的に支持されていた。ただ、そ のとき私は、同時受賞作である田久保英夫氏の『深い河』の方が好きだったが、彼らの同意は得られなかった。
作風の好みと言ってしまえばそれまでだが、地味で、簡素で、形容詞の少ない文体が好きなのである。その頃すでに、芥川龍之介の手に入る作品はすべて読んでいたが、最高だな、と読むたびに思ったのは、地味すぎるほど地味な『秋』という短編であった。
おそらく医学生になりたての頃に初めて読んだはずの『徳山道助の帰郷』は、最初はそれほど強い印象を受けた記憶がない。学生時代には、いいな、と思った本の中に傍線や書き込みをする悪癖があったのだが、この本はまっさらのままだ。今、昔の書き込みを見ると、恥ずかしさのあまり寝込んでしまいたくなるので、その意味でも、『徳 山道助の帰郷』とはそれからの長いつき合いが予想されていたのかも知れない。
信州の田舎町で医者の生活を始めてから二、三年目に小説を書き出した。最初の頃は気取りや見栄の鼻につく文章しか書けず、自分でもほとほと嫌になった。文を書く仲間の一人もいない田舎町で、それでもなんとかやってこられたのは「文學界」の編集者の厳しい激励があったのが第一である。しかし、何作か文芸誌に載せてもらえるようになると、もっと現代風な文体で、もっと読者に受けるような文章を書きたい、という変な欲が出てきた。背伸びをしたくなったのである。
そんなとき、誰から指示された訳でもないのに、『徳山道助の帰郷』を読み返してみた。
陸軍中将まで昇りつめた軍人の、退役後の落ちぶれた生活 を、帰郷のエピソードにからめて愛情深く淡々と記述していく文章が、つま先を立てて書きたがる私を、小説というのは本来こういうものなのだよ、とやさしく諭してくれるようだった。
山村の自作農家の長男として生まれた徳山道助が出世し、故郷に錦を飾る。若き日の彼にとって、故郷は山河までもがそのすばらしい出世ぶりを驚嘆しているように思えた。それが晩年になり、母の三十三回忌に帰ってみると、墓から見える風景が昔のままであり、死者たちの世界がひどく近しいものに感じられるようになった。この心境に至るまでの徳山道助の人生を、作者は簡潔で抑制の効いた、それでいてやさしさに満ちた文体で記述している。そして最後に、娘と孫たちが、骨になった道助を故郷に運ぶ彼の弟を東京駅 に見送るところで小説は終わる。作者の分身と思われる孫の満が、これがお祖父さんの本当の帰郷だったのかも知れない、と思った、と述懐する結びがいい。
『徳山道助の帰郷』というさりげないタイトルが最後になって生きており、豊かな読後感への案内役を務めてくれる。小説のタイトルとしては必要にして十分な条件を備えた稀有な例でもある。
この小説を書いたとき、作者の柏原兵三氏は三十三歳であった。そして五年後、三十八歳で亡くなっている。あえてこの若さで、と書かないのは、私が医療の現場で見ている死が、人の死は早すぎるが遅すぎるかのどちらかしかない、という先人のうがった警句どおりであることを認めざるを得ないからである。
この作品の中には、作者の死生観が色濃く投 影されているが、その枯れて深い様は、どう見ても三十三歳の男のものではない。多くの死と対面する医療従事者は、ある程度の年齢になると、楽観論者か運命論者になる以外、自らを生かし続ける自信がなくなるものだが、私は限りなく後者に近づいている。今、そんな視点からこの作品を読み直すと、作者はすでに書くべきことを書き終えたのではないかと思えてならない。
小説を自己の表現手段として選んだ者にとって、作品の中に自らの死生観を余すところなく表出し得たとしたら、それは至福と言うほかはないと思う。
こんな作品が書きたいと願って私は小説を書いてきた。今後も何度この本を読み返すことだろうか。あるいは、読み返さなくてすむ日が来るのだろうか。