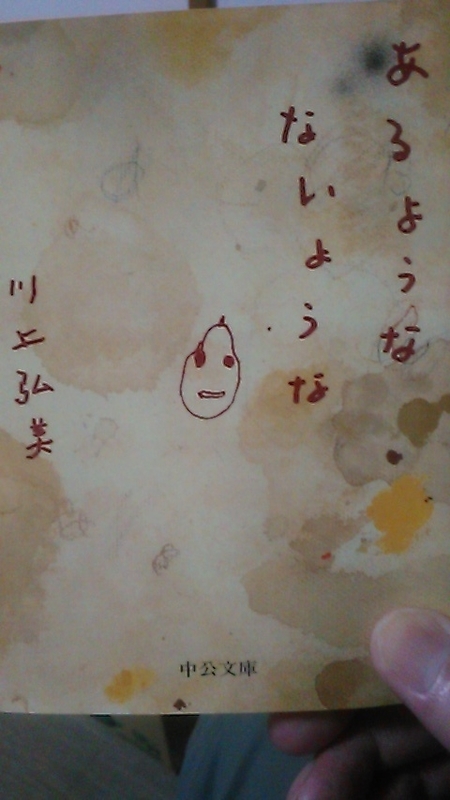
街の喫茶店に入ったら有線放送がかかっていて、そのとき聞いた曲がずいぶん印象に残ったのだった。何の曲だろうかと思い同席している友人に訊ねてみたら、SMAPの「夜空ノムコウ」だと言う。ずいぶん有名な曲なのに知らないの?と呆れられた。ごめんなさいね、と、誰に向かって謝っているんだか、頭を下げながら、手帳に曲名を書きとめ、早速帰りにCDを買った。はやり歌のCDを買うことがついぞなかったので知らなかったのだが、このごろは歌手の歌っている「元ヴァージョン」の他に、買った人間が一緒に歌うための「カラオケヴァージョン」も一緒にCDに録音されているのである。SMAPの歌う「夜空ノムコウ」の後に、私の歌ってもいいカラオケ用「夜空ノムコウ」が入っている。これはゆゆしきことである。ゆゆしく、嬉しく、恥ずかしい。恥ずかしくも嬉しく、私はこのカラオケ「夜空ノムコウ」にあわせて、一人「あれから~ぼくたちは~」などと、何回でもこそこそ歌ったことであった。
ところで、「夜空ノムコウ」を歌うにあたって、なかなかこれで葛藤もあったのだ。その葛藤とは何か。その葛藤こそは、この文章のテーマである「母と娘」の葛藤につながるものにほかならない。葛藤とは大仰な、そう思われるむきもあろう。しかし、母と娘との間にあるものは、たとえそれがどんなに仲良さげに見える母娘でも、なまなかなものではないのである。善し悪しではなく、その程度において。むろん私の母というものの間にあるものも、なまなかなものではない。以下にその「なまなかでないもの」を少しばかり記すことにするので、みなさままあ聞いてください。
私はいわゆる「ら抜き言葉」というものを使うことができない。「ら抜き言葉」とは、動詞に付いて可能形をつくる「られる」という助動詞を「れる」と省略するかたちの言葉づかいである。例えば、「食べられる」を「食べれる」と言う、そのような言葉づかいだ。文章の世界ではいっぱんにら抜き言葉はよくないものとされているようだ。歴史的に使用されてきた「られる」を「れる」にしては、格調がなくなる、というような理由によるものか。ところで現在私たちの日常の生活においては「ら抜き言葉」はごく普通に使われているし、また関東圏でない土地では元元の言葉が「ら抜き」であることも多い。ようするに「ら抜き」を「歴史的でないから悪し」とする姿勢もあれば「特にこだわらない」という姿勢もあるということであろう。個人的には、どちらの姿勢にも特に異存はない。ないので、私としては、「ら有り言葉」を使ってもいいはずだし、「ら抜き言葉」を使ってもいいはずなのだ。どちらもお好みに、というわけである。ところが、いざ「ら抜き言葉」を使おうとすると、私の体はがんとして反抗してしまうのである。
「食べれる」と言おうとしたとたんに、口がつぼまってしまう。「見れる」とワープロを打とうとしたとたんに指がちぢこまる。「喋れる」という、「ら抜き」とは認定されないかもしれない言葉でさえ、だめなのである。「喋れる」を消して、「喋ることができる」などという持ってまわった表現に直してしまう。
それはなぜか?
それはひとえに母からの「刷り込み」によるものなのである。
母は自称「東京人」である。先祖は「江戸の三辰」と言われた遊び人三人衆のうちの一人「なんとか辰五郎」であり(それが何の自慢になるのかよくわからないのだが、自慢になるものらしい)、三代どころか二十五代前まで辿ってもすべて江戸または東京の人間である。東京人たるもの、義理人情にあつく気っぷよくしかし人には立ち入らず、山手線の外側はすでに辺境の地、渋谷新宿は街とはいえぬ、繁華街ならば銀座、町ならば浅草上野、醤油は「おしたじ」お風呂は「おぃや(「お湯屋」が東京流になまったものらしい)」みそ汁は「おみおつけ」と言わねばならず、熊を「く」ま(く、にアクセント)などと言おうものなら平手打ちが飛び、驚いたときには「びっくり下谷の広徳寺、おそれ入谷の鬼子母神、そうは有馬の水天宮」とかんぱつを入れず叫ぶ。そんな母の口癖は「お茶のお稽古ではいつも馬生さん(故十代目金原亭馬生、ご近所だったらしいです)と一緒だったわ」であった。
その東京人の母が、「ら抜き言葉なんざ使っちゃいけませんよ」と、私に刷り込んだのである。むろん東京人としては、「ら抜き言葉」などという無粋な言い方はしなかった、「見れる食べれる、そんな言葉はナンですよ、東京の人間の使うものじゃありません、あなたはただでさえこんな田舎に住んでいるんだから(住んでいた杉並区を、母は「昔このへんに遠足で来たことがあった」と言って田舎扱いし、私のことを「田舎の子供」とあわれんだ)、アレね、言葉くらいは東京のものを使ってちょうだいね(「アレ」「ナンです」などの婉曲表現も東京人特有のものであるらしかった)」と、一週間に一回は言い言いするのであった。田舎(しつこいようだが、東京の杉並区である)に住 み、富山生まれの父を持ち、田舎の小学校に通う子供を、母はどうにかして「まともな」東京人に仕立てようとするつもりらしかった。
しかし、子供の郷土愛は強いのである。田舎のどこが悪い。渋谷も下北沢も吉祥寺も立派な繁華街だよ。おしたじなんて言っても誰にも通じないぜ。「く」まだろうがく「ま」だろうがどっちでもいい。世界は広い、ひとびとは多様である、東京がなんぼのもんじゃ、わしぐれたるで。
というわけで、ある年頃から、私の「東京嫌い」が始まった。母の言う「東京」らしい行動とはことごとく反対の行動をとり、「東京」らしい言葉づかいはせず、「東京」出身でない恋人をつくり、果ては結婚して東京を離れた。東京を離れて、どんなにか私はほっとしたことだろう。東京でない場所は、みなゆったりとした心暖かなひとびとの住む場所に思えた。関西の言葉はなんと柔軟なんだろう。名古屋のひとびとはなんて親愛感に満ちているんだろう。行く先々の土地で、私はよろこんだ。そして、次第に「東京」ひいては「母」からのある種の呪縛からのがれていった(ように思いこんだ)のであった。
ところがどっこい、である。
母の「東京」的呪縛からのがれきって「自由自在なココロ」を獲得したかに思いこんだのもつかのま、文章を書く仕事にたずさわるようになって、私は「ら抜き」を打とうとすると、指が反抗する。インタビューなどで「ら抜き言葉」を使うインタビュアーに会うと、指摘したくなってむずむずする。「ら抜き」的な表現を使うまいとして文章をわざわざ直し、煩雑な文章だてにしてしまう。
いくら、「ら抜き」だろうがそうでなかろうがどっちでもいいじゃない、と思おうとしても、だめなのである。ある時など、「ら抜き」を使ってしまった原稿のことを思い寝つかれず徹夜をしてしまったことがあった。
つまりは、それほどまでに母の刷り込みは強かった、ということになろうか。東京的なものから離れた行動をあえてとるというやり方も、実は母の刷り込みを意識しているということに他ならなかったのである。もしも真に「自由自在なここココロ」を持っているのなら、東京の中にいたって、ぜんぜんかまわないわけなのであるから。
母なるものからのがれ自由になろうとすることは、いかに難しいことであるか。
そこで、話はSMAPに戻る。「夜空ノムコウ」という曲の一節は次のようなものなのである。
あれからぼくたちは、何かを信じてこれたかなぁ.......
「これたかなぁ」
この部分が、私にとっては大いなる「葛藤」だったわけである。いつもならば、私は「これたかなぁ」にこだわってこの歌を歌えなかったにちがいない。ところがSMAPの力といおうか作詞家スガシカオ氏の力といおうか、「これたかなぁ」は、SMAPの甘く若々しい雰囲気と非常にぴったりしているのである。ら抜きでもかまわない、いや、それどころか、ら抜きでなければこの感じは出ない、それほどまでにこの場合の「これたかなぁ」はぴったりなのであった。
葛藤した。私は大いに葛藤した。しかし「これたかなぁ」のよろしさは強力だった。あまりに強力だった。そして、ついに私は長年の「ら抜き」への禁忌を克服したのだった。
四十歳になんなんとしている人間への、この母の強き呪縛、まさに「なまなかなものではない」でしょう。SMAPという全日本的に強力な若者たちの力を借りて、はじめて私は母からの「ら抜き」の呪縛をのがれることができたのであった。ありがとう、SMAP。
ただし、これくらいで「のがれた」などと言っているとは、甘っちょろいことである。「克服」「のがれた」などと言っている間は、呪縛が弱まっていないのだ。これからも、なまなかでない母と私の葛藤は続くにちがいない。あーあ。